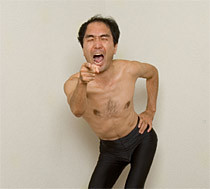スポンサーサイト
新しい記事を書く事で広告が消せます。
ネットに蔓延する疑似科学やデマに騙されない思考法とは
1:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/02/27(水) 13:13:36.14 ID:JxhKASRa0
ネットで繰り返し問題提起される「疑似科学」。なぜ人は欺されるのか、どう対処するればいいのか。
2010年科学ジャーナリスト賞を受賞し、「ゼロリスク社会の罠」の著者でもある佐藤健太郎氏に聞いた。(取材・文=フリーライター・神田憲行)
--疑似科学とは、どんなものを指すのでしょうか。
佐藤:はっきりした線引きは難しいのですが、もっともらしい用語をちりばめて科学を装いながら、科学的根拠がはっきりしないものを指します。多くは何らかの形でビジネスと結びついています。
--たとえばどんなものがありますか。
佐藤:典型は「ホメオパシー」でしょうか。200年前にドイツの医師が提唱した“医療行為”なんですが、レメディという砂糖玉を舐めれば人間の自然治癒力が高まり、病気が治るとされました。
これは原理的にも考えられませんし、治療効果もないことは厳密な試験で実証されています。
砂糖玉を舐めているだけでは毒にも薬にもならないですが、それだけで病気が治ると思い込んで、他の医療行為を拒否するところが問題になるのです。
疑似科学に共通するのは、「シンプルでわかりやすい」「博士やタレントなど広告塔になる権威付け有名人がいる」「意外性があって心に残る」といった点です。
わかりやすさでいえば、たとえば「コラーゲンを食べてお肌がツルツルに」という広告をよく見ますが、科学的な根拠は何もありません。
--疑似科学に欺されないためにはどうすればいいのでしょうか。
佐藤:「その情報が本当だとしたらどうなるか」をよく考えてみること。
擬似科学とはちょっと違いますが、今回の原発事故以降、「鼻血が出た、下痢をする」と放射線被害の心配をしている人がかなり出ました。
もしそんな症状が出るなら、福島の近くに行くほど鼻血や下痢を起こしている人が増えるはずですが、そうはなっていない。
上空を飛ぶために200マイクロシーベルトの被爆をしている国際線のパイロットや乗客は、みんな毎回鼻血を出してなければおかしい。
専門知識がなくとも、判別できることはいろいろあるはずです。
http://www.news-postseven.com/archives/20130225_173290.html
| Top Page |